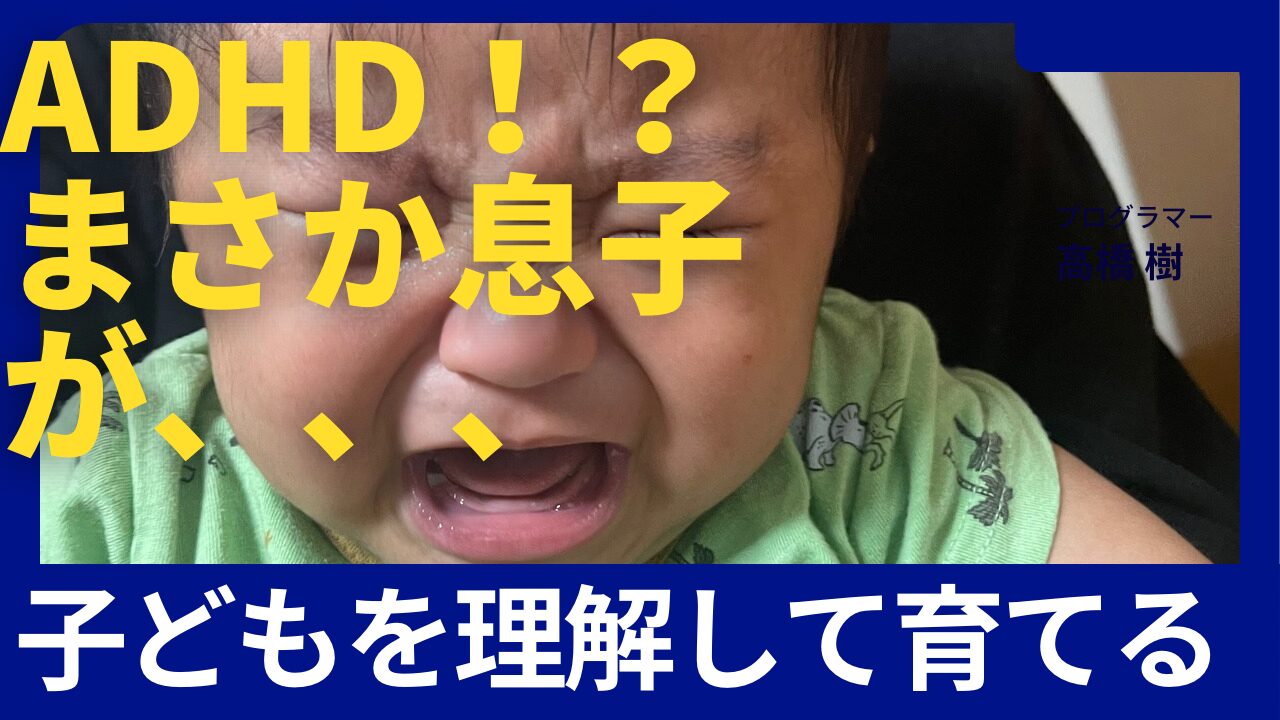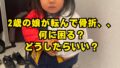「なんでできないの?」→ その考え方がしんどさを生む理由
児童養護施設で働いていると、ADHDの子に限らず、「どうしてこんな簡単なことができないの?」と思う場面によく出会います。
でも、たくさんの子どもたちを見てきて思うのは、「できない」のではなく、「できる仕組みが整っていないだけ」なのかもしれないということです。
たとえば、忘れ物が多い子どもに対して、大人は「ちゃんと準備すればいいだけなのに」と思ってしまいがちです。
でも、ADHDの子どもは、ワーキングメモリ(作業記憶)や注意の切り替えが苦手なことが多く、「今やるべきこと」を覚えておくのが難しいのです。
次の行動に移ると、さっきまで考えていたことをポロッと忘れてしまうこともあります。
「昨日も同じことで怒られたよね?」
「どうして何回言っても直らないの?」
こう言いたくなる気持ちは、とてもよくわかります。
でも、実は子ども自身も「やらなきゃいけないのは分かっているのに、また忘れてしまった……」と落ち込んでいることがあります。
そこにさらに叱られると、「どうせ自分はダメなんだ」と自己肯定感がどんどん下がってしまうのです。
では、どうすればいいのでしょうか?
「なんでできないの?」ではなく、
「どうすればできる?」に目を向けることが大切です。
たとえば、以下のような工夫があります。
- 持ち物チェックリストを玄関に貼る
- 宿題をやる場所を決めてルール化する
- ゲームの時間をタイマーで見える化する
などの工夫をする事で、子ども達の行動改善につながることがあります。
今までたくさんの子どもたちを見てきましたが、
「この子はこれが苦手なんだ」と理解すると、叱るよりも先に工夫できることが増えると感じています。
それに、子どもも「やっとできた!」という成功体験を積むことで、自信を持ち、少しずつ成長していきます。
「なんでできないの?」と感じるときほど、「どうすればこの子ができるようになるかな?」と考えてみることで、親も子どもも少し気持ちが楽になるかもしれません。
「ダメ!」が逆効果? ADHDの子が伸びる声かけのコツ
「なんでできないの?」ではなく、「どうすればできる?」に目を向けることが大切だとお話ししました。では、実際にどんな声かけをすれば、ADHDの子どもが前向きに成長できるのでしょうか?
私自身、児童養護施設でたくさんの子どもたちと関わってきましたが、「ダメ!」と否定するだけでは、ADHDの子どもは変わるどころか、さらに混乱してしまうことが多いと感じます。
もちろん、危険なことや人を傷つけることには「ダメ」と伝える必要があります。
でも、日常のちょっとした失敗やミスに対して、頭ごなしに否定してしまうと、子どもは「また怒られた」「どうせできないんだ」と自信をなくしてしまうのです。
ADHDの子に「ダメ!」が逆効果になりやすい理由
ADHDの子どもは、衝動的に行動してしまう特性があります。「やっちゃダメ」と言われても、考える前に体が動いてしまうこともあります。
たとえば、授業中に思いついたことをすぐ口に出してしまう子に、「静かにしなさい!」と何度言っても、また同じことを繰り返してしまう……。
これは、本人がわざとやっているのではなく、「どうしたらいいのか?」を具体的にイメージしにくいからなのです。
「ダメ!」の代わりに伝えたい声かけ
では、「ダメ!」の代わりに、どんな声かけが効果的なのでしょうか?
✅ 「こうしてくれると助かるな」
→「静かにしなさい!」ではなく、「今は手を挙げてから話してくれると助かるな」と伝える。
✅ 「次はどうしたらいいと思う?」
→「なんで忘れ物するの!」ではなく、「次はどうしたら忘れないかな?」と一緒に考える。
✅ 「できたね!」と成功体験を積ませる
→ 少しでもできたら、「さっき手を挙げられたね!」「プリントちゃんと出せたね!」とポジティブに伝える。
こういった声かけを意識すると、子どもは「自分にもできるんだ」と感じ、少しずつ成功体験を積んでいくことができます。
実際に、施設の子どもたちも、「こうするといいよ」と具体的に伝えると、行動が変わりやすいと感じます。
「ダメ!」を減らして、お互いに楽になる関わりを
ADHDの子どもにとって、「ダメ!」と言われることが多い環境は、とてもストレスになります。
もちろん、大人も何度も同じことを注意するのはしんどいですよね。
でも、「この子はどうしたら分かりやすいかな?」と考えながら声をかけるだけで、子どもとの関係がぐっと良くなります。
完璧にできなくても大丈夫。
少しずつ、「ダメ!」の代わりに伝えられる言葉を増やしていくことで、子どもも大人も、ちょっとずつ楽になれるはずです。
忘れ物・片付け苦手…どうしたら? 具体的なサポート法
さて先程では、「ダメ!」と否定するのではなく、「どうすればできる?」という視点を持った声かけが大切だとお話ししました。
でも、声かけだけで改善できるとは限りません。ADHDの子どもがうまくできないのは、やる気がないわけではなく、そもそも「できる仕組み」が整っていないことが多いからです。
その代表的なものが
「忘れ物」と「片付けの苦手さ」
児童養護施設で子どもたちと関わっていると、「昨日も言ったのにまた忘れてる!」「片付けなさいって何回言わせるの?」と、ついイライラしてしまう場面によく出くわします。
でも、「気をつけなさい!」と何度言っても、本人が意識できなければ変わるのは難しいんですよね、、、
では、どうすればいいのか?
子どもが「思い出しやすい」「やりやすい」環境を作ることで、忘れ物や片付けの苦手さをサポートできます。
忘れ物対策|「思い出す」仕組みを作る
ADHDの子どもは、目の前のことに集中しすぎて、次にやるべきことを忘れてしまうことがよくあります。だから、「忘れる前に思い出せる仕組み」を作ることが大切です。
✅ 玄関に「持ち物チェックリスト」を貼る
→ 文字やイラストでリストを作り、毎朝チェックする習慣をつける。
✅ ランドセルやバッグの中身を「セットの形」にする
→ 「筆箱はこのポケット」「プリントはファイルに挟む」と場所を決めることで、探す手間が減り、忘れ物も少なくなる。
✅ 「前日のうちに準備する」を習慣化する
→ 朝はバタバタしやすいので、「寝る前に準備する」ルールを決めると忘れ物が減る。慣れるまでは一緒にチェックするのも◎。
片付け対策|「戻す場所」と「戻すタイミング」を決める
「片付けなさい!」と言われても、ADHDの子どもにとっては「どこに片付けるのか?」「いつ片付けるのか?」が曖昧だと動きづらいことがあります。
✅ 「ここに戻す」を明確にする
→ 「ランドセルはこの棚」「ゲームはこのカゴに入れる」など、置く場所を決める。ラベルや写真を貼ると分かりやすい。
✅ 片付けのタイミングを決める
→ 「夜ご飯の前に片付ける」「寝る前におもちゃを箱に入れる」など、タイミングをルール化すると習慣になりやすい。
✅ タイマーを使って「ゲーム感覚」でやる
→ 「5分で片付け競争しよう!」など、遊びの要素を入れると楽しみながらできる。
環境を整えると、「できた!」が増える
「ダメ!」と叱るのではなく、「どうすればできる?」を考えて、環境を整えてあげることで、子どもも「できた!」という成功体験を積み重ねられます。そして、それが少しずつ自信につながっていきます。
忘れ物や片付けの苦手さに悩んでいる子どもに対して、「なんでできないの?」ではなく、「この子ができるためにはどうすればいいかな?」と、一緒に考えていけたらいいですね。
感情の爆発に振り回されない! 親も楽になる接し方
これまで、ADHDの子どもに対する「なんでできないの?」や「ダメ!」といった声かけや、忘れ物・片付けへの具体的なサポート法についてお話ししてきました。
今回は、親自身が感情の爆発に振り回されず、落ち着いた気持ちで子どもに接するための方法について考えてみたいと思います。
親も自分の感情に気づく
まず大切なのは、親自身が「イライラしている」と感じたときに、一度立ち止まることです。
児童養護施設で働く中で、たくさんの子どもたちの行動を見てきましたが、どうしても感情が先走ってしまうことがあります。
たとえば、同じ注意を何度もしなければならないと感じたとき、心の中で「もう我慢の限界…」と感じるのは自然なことです。
そんなときは、深呼吸をして「自分も一息つこう」と意識するだけでも、冷静な対応がしやすくなります。
感情のコントロールは環境作りから
前述のように、子どもができる環境を整えると成功体験が積み重なり、子ども自身も落ち着いて取り組むようになります。
同じように、親も感情に左右されずに対応できる環境作りが大切です。
たとえば、子どものルールやサポート方法を事前に決め、いつも同じ流れで対応することで、予測可能な状況が生まれます。
そうすることで、親も「次はどうなるだろう」と心配することが少なくなり、結果として自分の感情も安定しやすくなります。
子どもの失敗を受け入れる心構え
「なんでできないの?」とつい思ってしまうとき、どうしても自分の中で「期待と現実のギャップ」にフラストレーションが溜まります。
ADHDの子どもは、「できないこと」が多いと自信を失いやすいですが、親たちの工夫として、小さな成功体験を積み重ねることが効果的です。これにより、子どもは自己肯定感を高め、次に挑戦する意欲が湧いてきます。
しかし、ADHDの子どもは、努力してもすぐには成果が出にくいことが多いのです。
そうした場合、「失敗も成長の一部」と受け入れることが、親自身の心の負担を軽くします。
たとえば、子どもが忘れ物をしてしまったときも、「今回はうまくいかなかったけど、次は工夫できるかもしれない」と前向きな気持ちで次につなげると、感情の爆発も抑えやすくなります。
自分に優しく、周囲のサポートも活用する
最後に、親自身も「完璧にできなくても大丈夫」と自分に優しくすることが重要です。
児童養護施設で働く中で、同僚や先輩と情報交換をしながら、同じ悩みを共有することも大きな助けになります。
家庭でも、パートナーや友人と悩みを分かち合うことで、感情が高ぶったときの対処法を学び、実践することができるでしょう。
このように、感情の爆発に振り回されないためには、まず自分自身の感情に気づき、コントロールする環境作りと心構えが大切です。
そして、子どもの行動に対して「どうすればできるか?」を一緒に考えることで、親も子どもも落ち着いて前向きに取り組める環境が整います。
少しずつでも、双方が成長していけるような関係を目指していければ、親も楽になれるはずです。
「うちの子だけ?」と不安なあなたへ|育てるうえで大切にしたいこと
「なんでこんなに忘れ物が多いんだろう?」
「どうして感情が爆発してしまうんだろう?」
「他の子はできているのに、うちの子はなぜ…?」
ADHDの特徴がある子を育てていると、ふとした瞬間に「うちの子だけ?」と不安になることがあるかもしれません。
まわりの子と比べて、できないことが目につくと、「ちゃんと育てられているのかな」と心配になることもありますよね。
でも、児童養護施設でいろいろな子どもたちと関わる中で感じたのは、「子どもはそれぞれ違うし、それでいい」ということです。
発達のスピードも、得意・不得意も、一人ひとり違います。
だからこそ、まわりと比べて「できないこと」を数えるよりも、「この子にとって何が大切か?」を考えていくことが、親も子どもも楽になれる道なんじゃないかなと思います。
「できないこと」ではなく「この子に合った育ち方」を見つける
ADHDの子どもは、確かに苦手なことが多いかもしれません。
でも、それは「ダメな子」ということではなく、「自分に合ったやり方を見つければ、ぐんと成長できる子」だということでもあります。
たとえば、これまでのブログでお伝えしてきたように、
✅ 忘れ物が多いなら「思い出しやすい仕組み」を作る
✅ 片付けが苦手なら「戻す場所とタイミング」を決める
✅ 感情の爆発が起こるなら「クールダウンの方法」を一緒に考える
…こんなふうに、その子に合ったサポートをしていくことで、「できた!」という経験を増やすことができます。
「この子だからこそ持っている魅力」を大切に
また、ADHDの子どもたちには、「大人では思いつかないような発想ができる」「集中すると驚くほどの力を発揮する」「感情が豊かで、誰かをすごく大切にできる」といった素敵な一面もあります。
施設の子どもたちを見ていても、「すぐに気が散る」と思っていた子が、好きなことにはものすごい集中力を発揮したり、「感情の起伏が激しい」と思っていた子が、人一倍優しい心を持っていたりすることがよくありました。
だからこそ、「他の子と同じようにできるか?」ではなく、「この子の良さをどう伸ばしていけるか?」という視点で関わることが大切なのかもしれません。
親も「完璧じゃなくていい」
子どもの育ちに悩むとき、「私の関わり方が悪いのかな?」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。でも、育児に「絶対にこうすればうまくいく」という正解はありません。
子どもも親も、試行錯誤しながら一緒に成長していくもの。
うまくいかない日があっても、「じゃあ次はどうしよう?」と前を向いていければ、それで十分なのかもしれません。
「うちの子だけ?」と不安になったときは、「この子には、この子なりの成長のペースがある」と、自分に言い聞かせてみてください。 そして、「今のこの子にとって、一番大事なことは何かな?」と考えてみる。
そうやって、一歩ずつ、その子らしい育ちを見守っていけたらいいですね。
実際に効果があった! ADHDの子を持つ親たちの工夫
前回までで、ADHDの子どもに対するサポート方法についてお伝えしてきましたが、実際にADHDの子どもを育てている親たちの工夫には、どんなものがあるのでしょうか?
私も児童養護施設でたくさんのADHDの子どもたちと関わってきた中で、親や施設の職員が実践していた方法で「これは効果があった!」というものをいくつか紹介したいと思います。
これらの工夫は、ほんの少しのアイデアで、日々の生活をスムーズにしたり、子どもが自信を持てるようになったりするものです。
視覚的なサポートで「忘れ物」を防ぐ
ADHDの子どもは、どうしても「目の前のこと」に集中しがちで、次にやることを忘れてしまうことがあります。実際に効果があった方法として、「視覚的なサポート」を活用することが挙げられます。
✅ 持ち物チェックリストの作成
親が、子どもと一緒に持ち物リストを作り、それを見える場所に貼っておくと、朝の準備や学校に持っていくものの確認がスムーズになります。
リストに加えて、イラストや写真を使うことで、視覚的に分かりやすくするのもポイントです。
✅ 「準備完了シール」などの達成感を得る工夫
子どもが自分で準備したアイテムに「準備完了シール」を貼るなど、達成感を味わわせることで、自己管理への意識が高まります。
タイマーやアラームで時間の感覚を養う
ADHDの子どもは、時間の感覚がつかみにくいため、特に「時間を守る」ことが苦手です。そこで実際に効果があったのは、タイマーやアラームを使った時間管理です。
✅ タイマーで時間を区切る
「勉強は30分、それから10分休憩」というように、時間を具体的に区切ってやるべきことを明確にすることで、集中しやすくなります。
タイマーが鳴ると「次の行動」を自分で切り替えやすくなるので、時間を守る感覚も身につきます。
✅ アラームで「やるべきこと」を知らせる
「そろそろお風呂の時間だよ」「宿題を始める時間だよ」とアラームで知らせることで、突発的な状況でも心の準備ができ、スムーズに次の行動に移りやすくなります。
小さな成功体験を積み重ねる
✅ 褒めるポイントを細かく設定する
「勉強を1問解けたら褒める」「靴をきちんと揃えられたら褒める」といったように、できたことを小さな単位で褒めることで、子どもは自信を持つことができます。
褒める際には、「その行動がどんなに素晴らしいか」を具体的に伝えると、子どもは自分の成長を実感しやすくなります。
✅ 目標を小さく設定する
大きな目標をいきなり与えるとプレッシャーを感じやすいので、例えば「今日は10分間だけ集中して勉強しよう」といった小さな目標を設定することで、成功の経験を得やすくなります。
感情のコントロールをサポートする方法
感情の爆発に対して、親が冷静に接することが大切だという話をしてきましたが、実際に多くの親たちが取り入れていたのが、「感情の自己調整」を助けるためのツールや方法です。
✅ 気持ちを表現する「感情カード」や「気持ちボード」
子どもが感情をうまく言葉にできるように、感情のカードや気持ちを示すボードを使って「今、どう感じているか」を視覚的に表現することで、感情を整理する手助けになります。
✅ 冷静になる時間を作る
子どもが感情的になっているときに、深呼吸や「冷静になるための時間」を設けることで、感情を落ち着けるサポートができます。例えば、「2分間、静かな場所で過ごす」という時間を設けて、感情を整理させると、爆発を防ぐことができます。
親も一緒に学ぶことが大切
最後に、ADHDの子どもを育てるうえで、親自身が知識を深めることも大切です。実際に、親がADHDの特性や適切なサポート方法を学ぶことで、子どもの成長をより支えやすくなります。
✅ ADHDに関する書籍や講座を利用する
ADHDの特性や育て方について学ぶための書籍やオンライン講座を受講することで、日々の育児に役立つヒントを得られます。
親同士のサポートグループに参加するのも、情報交換や心の支えになります。
実際にADHDの子どもを持つ親たちが実践して効果があった工夫は、ほんの些細なことかもしれませんが、子どもにとっては大きな違いを生むことがあります。「小さな成功体験」「環境の工夫」「感情の整理」など、日々の積み重ねが大切です。
そして、親も完璧を目指すのではなく、少しずつやり方を試しながら、子どもと一緒に成長していけばいいんです。毎日の工夫が、子どもをより良い方向へと導いていくんだと思います。