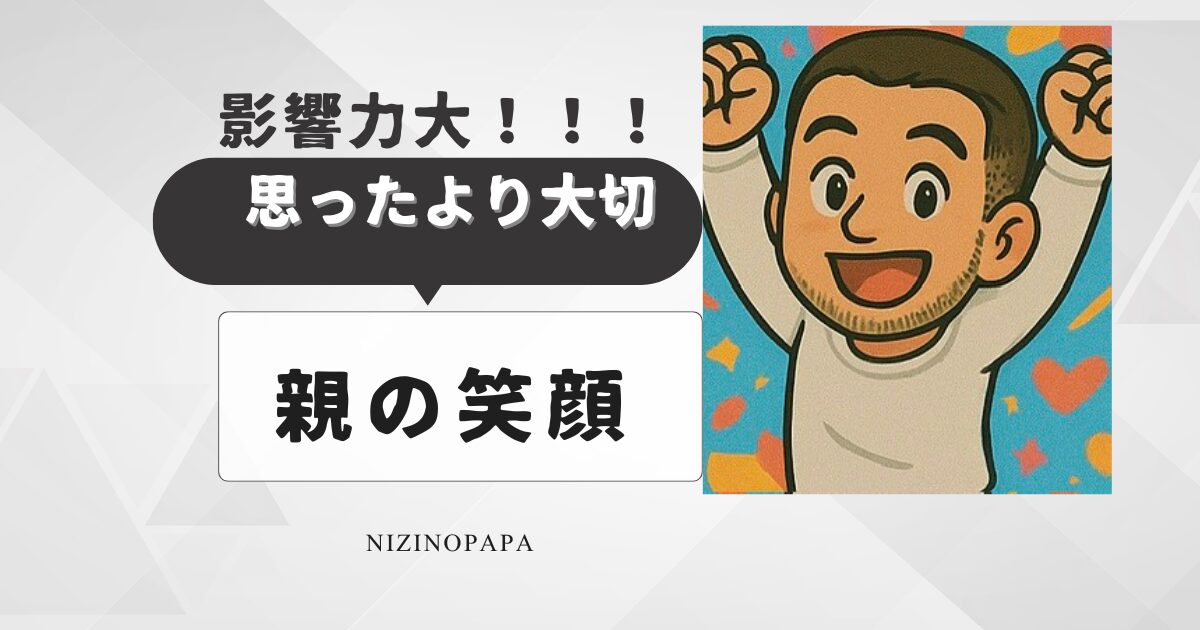親の「笑顔」は、
子どもの心にとって“安心のサイン”だといいます。
逆に、親のピリピリした空気感は、子どもにとっては目に見えないストレスになります。
しかもそれは、言葉じゃなくて“肌”を通じて感じ取られるそうです。
子どもはまだ言葉が分からない分、親の雰囲気や気配に敏感なんですね。
そして、その空気感で育った子は、将来、自分が親になったときに、同じような空気感を知らず知らずのうちに出してしまうこともあります。
私達親は、それに「気づけた瞬間」から、ちゃんと変えていける。
それが大人の、親の、すごい力なんです。
今回は、保育園で40年以上勤めた先生の話をもとに、私の経験も交えながらお伝えします。
子育てに悩む親へ、そして、未来ある子ども達のために。少しでも届くようにと願いをこめて。
肌で感じる“安心”を、大人から学ぶ子どもたち
大人って、ストレスを「声の大きさ」や「表情の怖さ」から感じることがありますよね。
誰かが怒鳴ってたり、険しい顔してたりすると、「うっ…」ってなる。
でも子どもはそれだけではありません。
まだ言葉の意味も分からないから、「空気」そのもので感じ取ることがあります。
例えば、
- 抱っこしたときの腕の力の入れ具合
- 呼吸の浅さ
- 表情のかすかな動き
- 声のトーン
そういうのを、まるで“肌で吸収する”みたいに感じ取ってるんです。
このことを、
心理学では「情動調律(じょうどうちょうりつ)」って言います。
…って、なんだそりゃですよね(笑)
簡単に言えば、「大人の心のリズムに、子どもの感情も影響を受ける」ってことです。
親が落ち着いていれば、子どもも落ち着ける。
親がイライラしていれば、子どもも不安になる。
そんなふうに、
子どもは“安心の仕方”を親から学んでいるわけです。
ピリピリした空気は、“酸性の家庭”のサインかも?
娘の通う保育園の父親参観日でのこと。
園長先生からの話で、
「家庭の空気が“酸性気質”になってないか?」という問いがありました。
これ、最初聞いたとき「なんの話?」って思ったんですけど、つまりはこういうこと。
- ピリピリしてる
- トゲトゲしてる
- なんとなく怒ってる感じがする
- 誰も何も言ってないのに、息が詰まる
…そんな「家庭の空気」のことです。
子どもにとっての世界は“家庭がすべて”
だから、そういう酸っぱい空気の中で育つと、
「なんか、自分が悪いのかな…」って、勝手に自分を責めちゃう。
それが、子どもの自己肯定感にじわじわと影響するんです。
育児の「クセ」は、親から子へ引き継がれていく
育児現場でよく聞くのがこの言葉
「気づいたら、親と同じように怒鳴ってた」
「自分も叩かれて育ったから、つい手が出そうになる」
「厳しく育てられたから今の自分がいる。だから厳しく育てたほうが子どもは伸びる」
こういうのを、「世代間連鎖(せだいかんれんさ)」って呼んだりします。
難しそうな言い方だけど、要は「自分がされたことを、無意識に再現してしまう」ってことです。
でも、ここがポイント。
「連鎖を断ち切れるのは、気づいた人だけ」
自分の育ちに向き合って、「ここは変えたい」と思える人には、
ちゃんと次の世代を守る力があるんです。
「伝わる空気」を変えるのは、こんな小さな一歩から
うちには、2人の子どもがいます。
夜、寝かしつけでこっちもクタクタのとき、上の子がなかなか寝てくれなくて…。
心の中では「もう、はやく寝てくれ〜」って思ってたんですよ。
でも、言葉に出さなくても、子どもが私の顔をじーっと見てきて。
で、めっちゃ不安そうな顔してたんです。
そのとき、「あ、これ、伝わってるな」って分かったんです。
私は声を荒げたわけじゃない。
でも、顔や呼吸、空気感が「イライラしてる」って伝えてしまってた。
だから、深呼吸して、「ごめんね、パパも疲れてたんだ〜」って言ってみました。
そしたら、子どもがニコッとして、スッと布団に入っていった。
そのあとはお互いゴロゴロしながら抱きしめて寝てくれました。
たぶん、あの瞬間、「パパ大丈夫なんだ」って安心してくれたんだと思います。
子どもの心に届くのは、完璧な言葉じゃなく“笑顔”の温度
子どもは、親の「顔」や「声」や「空気感」から、毎日安心感を吸収しています。
どんなに小さなことでもいい。
「今、自分がどんな空気をまとってるか?」
それにちょっと気づくだけで、子どもとの関係はやわらかく変わっていきます。
完璧な親じゃなくて大丈夫。
笑顔がいちばんのプレゼントなわけですね。
今日、1回でもいいから深呼吸してみましょう。
そして、自分に「お疲れさん」って言って、ちょっとだけ笑ってみましょう。
その一歩が、子どもの未来をほんのりあったかくしてくれるはずです。