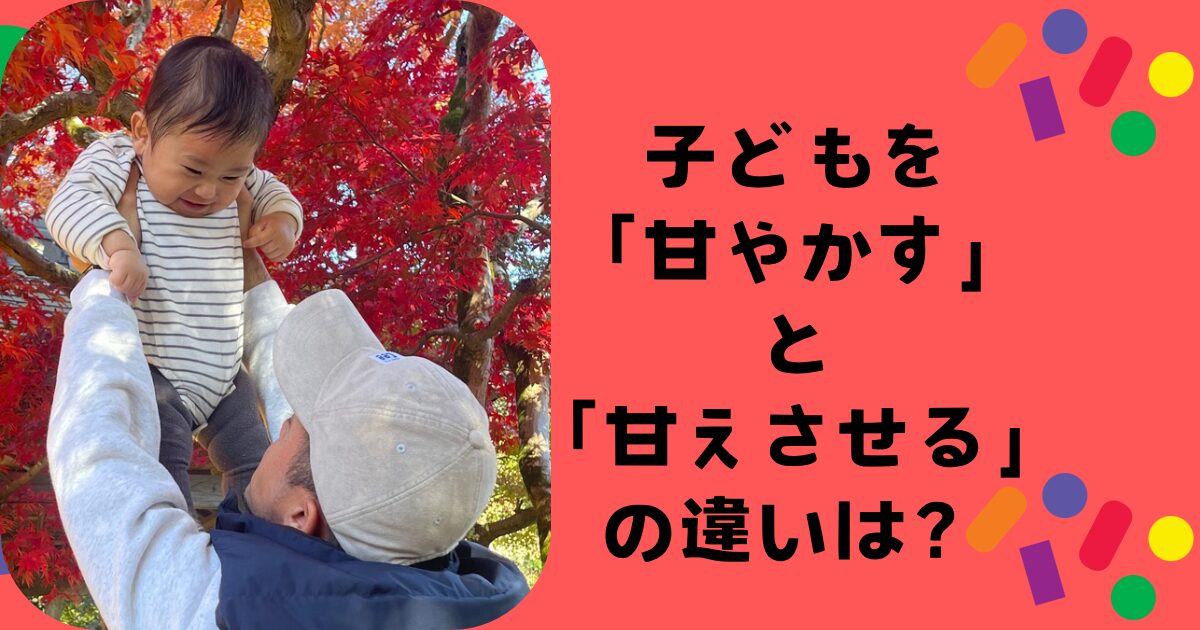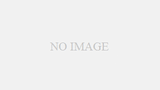※この記事では、A君という小学生の話が出てきますが、実在する人物ではありません。
こんにちは、2児のパパです。
家では子どもたちと向き合う日々、そして仕事では児童養護施設で暮らす子どもたちと関わる日々を送っています。
普段、私は温厚と言われることが多く、自分の意見は控え目な性格で人と争うことが苦手です。
施設の支援では、甘えさせると甘やかすということに対して、度々議論になることがあります。
様々な視点を持った施設職員が話してきた事をもとに、皆さんにもその違いを知って頂き、子育てに役立てて頂けたらと思います。
今日のテーマは
「甘えさせる」と「甘やかす」の違いについて。
加えて愛着障害の子の難しさを交えながら、私ならでは伝えられることを記事にしてみました。
A君の事例から学んでみよう!
小学生のA君(架空人物)のお話をします。
A君は小学校低学年の男の子。
児童養護施設で暮らしていて、明るく元気な子です。髪の毛は眉にかかる程度の長さで、笑った時の目元はくしゃっと崩れる、なんとも可愛らしい子です。
でも、深く関わるほどに、心に大きな傷を抱えていることがわかります。
彼の幼少期は、親からの虐待に苦しむ日々でした。
泣けばうるさいと暴力を振るわれ、父親から母親へのDVは日常的でした。
「僕はなぜ大切にしてもらえないんだろう。」
「パパ、ママ。僕ここにいるよ。仲良くしてよ。」
悲痛の叫びが聞こえてくるような気がします。
彼が親元を離れて施設に繋がったのは4歳の時。始めは全く問題を感じられないおとなしめの子でした。
しかし、小学校に入ると一転。
いわゆる「お試し行動」という問題行動が多く見られる子になりました。
たとえば、大人を困らせるようなことをわざとしたり、「どうせ僕なんて」と自分を卑下するようなことを言ったり…。
これは、大人に「本当に自分を愛してくれるの?」と確かめようとする行動です。
自己肯定感が低いあまりに、そうやって大人との関係を確認するしか術がないのです。
そんなA君が、不登校になったのはちょっとしたことがきっかけでした。
学校で友達と言い合いをしたこと。
「もう誰も自分を受け入れてくれない」と感じさせるほど大きな出来事になってしまったのえます。
子どもはみんな甘えたい
施設で暮らすA君の様子を見ていると、彼が心の底では「誰かに甘えたい」と思っていることがよくわかりました。
でも、虐待の経験から甘え方がわからず、大人に反発したり、ゲームに没頭したりしてしまう。
そんな彼に必要だったのは、
甘えられる環境
でした。
職員は
ここで大事なのが、「甘えさせる」と「甘やかす」の違いです。
• 甘えさせる:子どもの心を受け止め、安心して頼れる環境を作ること。
• 甘やかす:子どもの欲求を全て無条件に受け入れ、成長の機会を奪うこと。
たとえば、A君が宿題をしないといけない時。「もう無理!やりたくない。ゲームする!」と投げ出したときどうするでしょう。
ただ「やりたくないならあとでいいよ。先にゲームしようか。」とゲームを許し続けるだけでは甘やかすことになります。
でも、「無理にやらなくていいけど、一緒に少しずつ考えてやってみようか」と寄り添い、取り組むことで、甘えさせる環境を作ることができます。
要するに、
子どもの困り感は何かを察し、大人が手をかけてあげること
私はこの感覚がとても重要だと思います。
甘えさせる工夫
A君の支援では、次の3つを意識しました。
- 小さな成功体験を積む
- 感情を受け止める
- ルールを決める
小さな成功体験を一緒に作る
A君はゲームが大好きだったので、それを入り口にして、「これ、どうやったら勝てるの?」と興味を持つようにしました。
彼が得意なゲームの話をたくさん聞いて、「すごいなぁ、A君ってこういうことに気づけるんだね」と褒める。
それを繰り返すうちに、少しずつ「自分にはできることがある」と感じてくれるようになりました。
一見すると、ゲームを助長しているだけのようにも見えますが、ここのポイントは、A君の承認欲求を、満たす事です。
満たされなさがゲームに向いているのであれば、まずは存分にさせてあげながら、
その状況を一緒に過ごし、放っておかないこと
これがもの凄く大切です。
(2) 感情を受け止める
A君が「学校なんて行きたくない!」と怒りながら話すとき、「そう言うと怒られるかもって思ったんだね。
でも、その気持ち、ちゃんとわかるよ」と伝えました。
感情を否定せず、「ここなら安心して話していいよ」と感じてもらうことが、甘えさせる第一歩でした。
(3) 甘やかさずにルールを伝える
とはいえ、甘やかすことはしませんでした。
ゲームの時間を決めたり、約束を守らなかったときは一緒に振り返ったり。
優しく枠組みを示すことで、「自分の行動に責任を持つ」ことも少しずつ学べるようにしました。
5. パパとして感じたこと
2児の父親として、A君に向き合う日々は自分自身を振り返る時間でもありました。
私の家でも、子どもたちはよく「パパ、見て!」「これ手伝って!」と甘えてきます。
そのたびに、つい「今ちょっと待って」と言ってしまう自分がいて、反省することもあります。
でも、A君と過ごす中で気づいたのは、「甘えさせること」が子どもにとってどれほど大事かということです。
甘えを受け止めてもらった子どもは、「この人は自分を大切にしてくれる」と感じ、少しずつ自信をつけていきます。
それは、A君が「学校に行くのも悪くないかも」とつぶやいてくれたときに強く感じました。
6. おわりに
親や支援者が子どもにできることは、「甘えさせる」環境を整えることだと思います。
甘えさせない事が自立に向けた支援ではなく、甘えさせることで自立します。
「甘えさせる」という事はいい甘えであり、「甘やかす」とは根本的に違います。
子どもの心は、親に十分に依存し、安心感を得ることで成長します。
子どもは、親に依存した後に、不自由を感じ、また自立に向けて挑戦するのです。
いわば親の元というのは、充電場所のようなもの。
親として、甘えさせる時は存分に甘えさせ、自立に向けて飛び出そうとする我が子を「よし、行ってこい」と見送る。
そんな事を繰り返しながら大人になっていくという過程を知っておく事で、少し余裕が持てるのではないでしょうか。
子どもが安心して自分をさらけ出せる場所を作る。
それが、彼らの未来を支える第一歩になるんです。
「甘やかす」とは違う、「甘えさせる」という支え方。一緒に考えてみませんか?